|  |
|
|
|
|
|
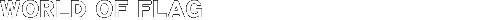
FLAG外伝 第1章 /野崎 透
4.幕間
国連軍が初めて地域紛争に本格介入するというニュースは、ウディヤーナの様相を一変させた。それまでは、むしろどこか遠くの知らない国で起きている事件の観があった紛争は、この報道を境に“金になる内戦”へと変貌し、中世の佇まいを残す古都スバシはゴールド・ラッシュよろしく大挙して押し寄せてきたジャーナリストでたちまち溢れ返ったのである。
スバシの旧市街にあるフリー・ジャーナリスト達の根城も一気に馴染みの顔が増え、まるでちょっとしたプレス・センターの様な賑わいを見せ始めた。もちろん、増えたのは紛争地で嫌と言う程見てきた顔ばかりではない。どこでこの酒場の事を聞き付けたのか、そこには新しい顔もちらほら混じっていた。
もっとも、そういった連中が簡単に仲間として受け入れられる程、このコミュニティーは寛容ではなかったが。
もう一つ、この宗教の街には、全く異なる性格の報道陣も押し寄せて来ていた。それは国連軍によって正式に取材許可が与えられたジャーナリスト達——つまり当局による便宜の供与が約束されたお抱え報道集団だった。
ベトナム戦争で大きく変貌した軍、或いは政府と報道との関係は、1991年の湾岸戦争や、続く2003年のイラク戦争において再び大きく変る事となる。ベトナム戦争敗戦の原因が自由な報道による厭戦気分の蔓延にあったと考えた米軍が、これらの中東の戦いで報道をコントロールする全く新しい方策を試みたのだ。それは、膨大な報道陣を自分達の懐に取り込み、恣意的(しいてき)に選別された情報を膨大にその目と耳に注ぎ込む事で、自分達に都合の良い報道だけを世界中に配信させようというものだった。
具体的に米軍が行ったのは、大手新聞社や放送局をバックにするジャーナリスト達に対して正式な許可を与え、可能な限りの全面的な協力を約束するというものだった。その中には、前線部隊への帯同取材をも許可するという、従来では考えられなかった便宜の供与すら含まれていた。
こうして、世界の報道は多国籍軍が与えた圧倒的な量のニュースで埋め尽くされ、邪魔な報道はほとんど掻き消される事となったのである。正に、米軍が試みたジャーナリストの“エンベッド(抱え込み)”は思惑通りに機能した様に見えた。
しかし、それはあくまで表面的なものに過ぎなかった。自ら展開したキャンペーンで自分達が如何に多くの大切なものを失ったか、その事に政府も軍も気付くべきだったのだ。
つまり、報道はどんな効果があるかではなく、どのような価値があるかで判断されるべきだという事である。
本来、権力にとっては多様な報道こそが自らの行動を判断する指標であるはずだった。近代民主主義が報道の自由を絶対的な原則として掲げているのは、もしそれが失われれば、権力は最早自らの暴走にブレーキを掛ける事が出来なくなり、結果的に国を過った方向に導いてしまうからだった。その事が端的に示されたのが、報道を窒息させる事によって自己修正の能力を失い、世界を悲劇に巻き込んでしまった第二次世界大戦のドイツであり、日本であったはずだ。
ところが、結果的にアメリカもまた同じ轍を踏む事となる。イラクへの侵攻は、まさに報道を窒息させてしまった為に自己を制御出来なくなった大国の暴走以外の何物でもなかった。ところが、中東に破滅的な混乱と数え切れない程の無益な死を残したこの戦争で世界の多くの軍が得たのは、全く別の教訓だった。侵攻当初、世界中の報道が圧倒的な管制報道の洪水に犯されたという事実は、各国の軍関係者をして、エンベッド・ジャーナリスト達の有用性をむしろ認識させる結果となったのである。
その中には国連軍も含まれていた。
スバシで活動していたフリー・ジャーナリスト達は見た。国連軍の侵攻と共に膨大なエンベッド・ジャーナリスト達が流れ込んで来るのを。
そして、国連軍が現地本部を置いたスバシのホテルで毎日の様にブリーフィングが開かれる様になるのを見て、知った。自分達にとっての新しい戦いが始まった事を——
酒場のコミュニティーに加わった新顔の中には日本人も一人いた。だが、こういう場所では自分から話し掛けない限りまず誰も相手にしてくれない事をその日本人は知らなかったのかもしれない。頻繁に酒場に顔を出しても、いつも隅の方でじっと周りの会話に耳を傾けるばかりで、自分がその輪の中に入る事はほとんど無かった。
その日本人に最初に語り掛けたのはリサだった。もちろん同情心からではない。珍しくこの酒場に若い女性がやって来たので、言葉を掛けてみたのだ。
もっとも、英語がそれ程得意ではないのだろう、日本の若い女性はリサの質問に対して、折れた木の切れ端の様に断片的な言葉を返すだけだった。それでもリサは、不器用な会話の中から相手の名前、“シラス・サエコ”を拾い上げる。そして、“for the first time”、つまり、このウディヤーナが初めての実戦である事も。
さらにリサにはもう一つ気付く。それは、危なっかしい言葉を交わしている間も、相手がカメラを手から離そうとしない事だった。機種は今ではもうすっかり珍しくなった銀塩の、しかもマニュアル・フォーカス・カメラだった。もちろん、傍らに置かれたカメラ・バッグの中にはディジタル・カメラも顔を覗かせていた。しかし、感触を確かめる様に始終絞りリングを回しているその手付きを見るまでもなく、どちらにより愛着を抱いているかは明らかだった。
何となく気持ちが込み上げて来る。知らず知らずの内に、リサは訊ねた。
「Nikon F3 ?」
サエコが嬉しそうな笑みを浮かべて答える。
「Yes.」
続いて語られた言葉を、しかし、リサは全く理解出来なかった。恐らくは日本語だったのだろう。ただ、カメラについて喋っているだろう事だけは、時々聞こえて来る単語からも窺えた。カメラに話題を振った途端、相手の顔から屈託が消えたのを見ている内に、リサはふと、全く同じ旧式カメラを愛用している人間がいる事を思い出した。偶然かどうか分からないが、そのカメラマンもまた日本人だった。
赤城を知っているかサエコに尋ねてみようか……そんな考えが一瞬リサの脳裏を過る。しかし、直ぐに思い直した。考えてみたら、二人はもう何度もここで顔を合わせているのだ。もし互いに知り合いなら、とっくに声を交わしているはずだった。ところが、リサが知る限りそんな事はまだ一度も無い。
“そうね、日本人同士と言っても、全然知らない方が普通よね”リサはそっとサエコの顔を窺いながら考えた。
初めて戦場の取材に来たという女性カメラマン……きっと不安なんだろうな。リサは自分が初めて戦場を取材した時の事を思い出した。
初めて表舞台に躍り出た国連軍ではあったが、既に様々な紛争地域で活動してきたスタッフが多く参加していた事が大きく寄与したのだろう、ウディヤーナでの活動自体は地に足の着いた着実なものだった。先ず解放軍が設置していた検問所の廃止や電力を始めとするライフラインの回復等といった、庶民の生活に直接関わる問題の解決を優先させた施策はウディヤーナ国民に好意をもって迎えられ、当初の警戒心も急速に薄れて行った。
もし国連軍がそのまま当初の方針を堅持していれば、この介入は後に成功と呼ばれる事になったかもしれない。しかし、この組織は内にあまりにも大きな矛盾を抱えていた。
安保理を中心とする大国の利害の衝突である。
最初にその問題が顔を覗かせたのは、停戦実現へ向けた全武装勢力参加の和平会議の呼び掛けが行われた時だった。当初、国連軍は過去の経歴を問わず全ての武装勢力を会議に参加させるつもりだった。ところが、会議開催の直前になって、P5の一国が国際的なテロ組織との関与が疑われている武装組織に関しては停戦交渉に参加する資格は無いと、一部の武装勢力の参加に対して意義を唱え始めたのである。
国連軍にとっては正に晴天の霹靂だった。既に会議の準備は最終段階を迎え、多くの武装勢力の幹部がスバシに集まっていた。もしここで会議を中止するような事があれば、武装勢力の強固な反発を招くのは必至だった。
しかし、国連軍による必死の説得にも拘わらず、P5の一国は頑として態度を変えず、ついには拒否権を振り翳して和平会議を葬り去ってしまうのだった。
あまりにも身勝手な行動だった。そこには明らかに自国以外の人間の感情に対する徹底的な無関心があった。恐らく、この大国の指導者達の頭の中には、こんな小さな国の人間が誇りを持っているなどいう考えは全く無かったのだろう。
だが、現実は逆だった。ウディヤーナの各地に割拠して来た武装勢力の指導者達は、誰よりも誇りを尊ぶ戦士達だった。
国連軍の呼び掛けに応じてスバシまでやってきた武装勢力の指導者達は、目前でこの聖地への入場を拒まれた時、それを侮辱と受け止めた。その汚名を雪(すす)がない限り、自分達の故郷へ帰る事は出来ないと考えた。
スバシを目指していた小さな流れは、一つ、また一つと合流を始める。そして、次々と怒りを呑み込み、一本の大きな河となっていった。
国連軍が停戦会議の初日として選んでいた望月の朝、怒りの大河は奔(わ)しる流れとなってスバシへと移動を始めた。平和への第一歩を記すはずだった日は、こうして惨劇の幕開けへと姿を変えたのである。
赤城は武装勢力の侵攻を、取材中の病院で聞いた。しかし、そのまま取材を続けた。
リサはソンタイと共に旧市街を駆け回っていた。あちこちに死体が散乱していた。ソンタイは、写真を撮るのも忘れ、NGOと共に怪我人の介護を始めた。リサはその姿を見て、カメラをバッグに仕舞った。
白洲冴子は、初めて見る戦争の凄惨さに、ただ呆然とうろつき回るだけだった。
その頃、エンベッド・ジャーナリスト達は、国連軍の協力の下、衝撃のスクープを世界に向けて配信し続けていた。
クリスは、ニュースをヨーロッパの演習場で観た。訓練と実験は、スケジュール通り続けられた——
|
|
|
|
|