|  |
|
|
|
|
|
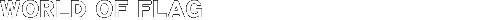
FLAG外伝 第1章 /野崎 透
3.特殊部隊(1)
電子偵察機から送られてきた映像は、目標周辺に脅威となるレーダーが存在しない事を示していた。クリスは指先のトグル・スィッチで、ポイントをモニター上の所定の位置へ移動させながら、次々とウィンドウを開いた。落下速度、対地高度、円柱座標系で示された加速度成分、アップデートされた予測降下ポイント……。
不意に、薄いキャノピーを通して伝わってくるジェット・エンジンの音が低くなる。それを聞いて、クリスは今自分達を運んでいる輸送機が高度を下げ始めた事を知った。その事を示す様に、シートが突き上げる様に振動し始める。地上付近の不規則な突風—ガスト—による振動だ。
クリスはディスプレイをカーゴベイ内の映像に切り替えた。しかし、画面には何も映らない。目標を目の前にして、貨物室内の照明を全て落としたのだろう。もちろん暗視モードに切り替えれば内部の様子を見る事も出来るが、そこまでするつもりはなかった。
その時、ヘッドセットに音声が流れてくる。
「トーラスよりハーカス1、最終確認、……」
上空を飛行している空中指揮管制機の指示だ。淡々とした口調で、これから行われる作戦の最終的な実行命令と、許容されている行動の範囲とが語られる。しかし、何れも既にプリブリーフィングで確認済みの事項だった。それを、こうして突入前にもう一度確認するのは、万が一予期せざる事態が出来(しゅったい)した場合に責任が司令部へ及ぶ事を避ける為だった。
確かに今の国連軍は派遣国から独立した組織になっているが、かつての寄り合い所帯だった時代の感覚は、そう簡単に抜けるものではない。それがこうした責任回避の姿勢となって表れて来るのだろう。
もっとも司令部が過度に慎重になっているのには、もう一つ別の理由があった。それはクリスが率いている部隊自身の性質だった。コードネームで“シーダック”と呼ばれているクリスの部隊は、公式にはまだその存在が認められていない特殊部隊なのである。
加盟国の基本的な合意の下に創設された国連軍にとって、その活動内容を公に出来ない特殊部隊の存在は、まさに諸刃の剣だった。しかし、20世紀末から21世紀に掛けて劇的に変質した戦争が、従来の正規軍的部隊に代わって特殊部隊の必要性を増大させてきている中で、その必要性は最早否定出来ないものとなっていた。
一方で、戦争はマスコミを中心としたイメージ戦としての性質を益々強めてきてもいた。つまり、特殊部隊は戦術的な必要性が高まる一方で、政治的には未だに負の側面を強く持つ存在だったのである。
各国の軍隊が特殊部隊の存在を公式には認めていない、つまりグレーゾーンのままにしているのは、戦術的な必要性と共に、その政治的なマイナス面を意識してのものでもあった。実際、21世紀初頭に行われた米軍のアフガニスタン侵攻では、デルタ・フォースが多くの局面で実質的に攻撃の主力を担ったにも拘わらず、その活動が報じられる事はほとんど無かった。同じ事は、続くイラク戦争でも起きている。全ては、特殊部隊の活動を可能な限り秘匿したいとする、軍と政府によるイメージ操作の結果であった。
しかし、同じ様な方法論を国連軍は採る事は出来ない。何故なら、国連軍の活動には200に及ぶ加盟国の合意の必要であり、結果として、どこの軍隊にも求められていないレベルでの厳密な情報公開の義務が課せられているからである。
国連軍に軍事機密が存在してはいけない。もしその様なものを認めれば、公平な紛争の調停者としての自己の存在を否定する事になってしまう。国連軍は、あくまで世界に対して開かれた軍隊でなければならなかったのだ。
ここで、結果的に国連軍は一つの方便を用いる。純然たる技術開発を目的とした実験部隊という名目の下に、特殊部隊を創設したのだ。
もちろん実験部隊である以上、実戦への投入は公式には認められない。だが、特殊部隊が投入される様な作戦の多くは一般的に外の目に触れる事がほとんど無いというのもまた事実だった。つまり、たとえシーダックを実戦に投入してもその殆どは秘匿出来るし、もし何らかの形で公表せざるを得なくなった場合でも、慎重に処理すれば実験という名目で糊塗(こと)する事も出来るであろうと考えられたのである。
今回の作戦も公式には実験であった。もちろん、その実体が一般に知れ渡れば、議論を巻き起こすのは必至だった。だからこそ、司令部も命令の内容には勢い慎重になるざるを得ないのである——
「……以上、検討を祈る」「チェック・ポイント、デルタ、通過。ハーカス1、2、これよりカウントダウンを開始します」
指揮官が最後の指示を告げると同時に、カウントダウンの開始を告げる機長の機内通信がヘッドセットを叩いた。クリスは瞬時に意識を切り替え、全てを現在進行している現実へと引き戻した。
いよいよ実戦か……急き立てるようなカウントの声を聞きながらも、クリスは自分がいつもの様に冷静である事を感じていた。本来ならばもっと緊張して良いのかも知れない。もちろん、クリス自身、これまで幾度も実戦をくぐり抜けてきたベテランであり、その意味では緊張を感じなくて当然なのかもしれない。しかし、少なくともシーダックに配属になってからはこれが初めての実戦なのである。
その事を彼女が初めて実感したのは、カウントが30を切り、輸送機の後部ランプがゆっくりと開き始めた時だった。それまでただ漆黒に覆われていたカーゴベイ内の画像が、ランプの隙間から差し込んできた光にゆっくりと切り裂かれ、押し広げられる暗幕の陰から、野戦車輌を少しだけ大きくした特異な形態の戦闘兵器が2機、少しずつ姿を現す。
HAVWC——高機動多機能ウェポン・キャリアー、通称“ハーヴィック”。国連軍に特殊部隊シーダックの創設を決心させた新世代の機動兵器である。
クリスはディスプレイの画像を見ながら、今自分がその内の1機に収まっているという現実に奇妙な違和感を覚えずにはいられなかった。しかし、間も無くクリスはこの機動兵器共々輸送機の後部ランプから放り出されるのだ。10メートル下を時速250キロという相対速度で移動している地面に向かって。
「15……」機長の声と共にランプがガクンと静止する。いよいよだ。クリスはディスプレイをハーヴィックの機上カメラに切り替えた。正面から捉えた後部ランプ開口部の画像が現れる。四角く切り取られた空隙(くうげき)の向こうを、赤茶けたマーブル模様が猛烈な勢いで流れていく。クリスは改めて降下ポイントが砂礫に覆われた台地の上である事を思い出した。
超低空飛行する輸送機からの降下は、これまでも繰り返し訓練してきていたが、それは何れもアリゾナの砂漠か、北ドイツの草原地帯で行われたものであり、こうした荒地への降下は初めてだった。
しかし、今は砂礫地帯へ降下する危険性について考えている余裕は無い。クリスは神経を全てディスプレイ上の数字に集中させた。
「10……5、4、3、2……投下」
機長の指示と同時に後部ランプの外に真っ白な花弁が開く。ハーヴィックを引き出すドラッグシュートだ。その瞬間、猛烈なGがクリスの身体をシートに叩き付けた——
和平交渉を何とか軌道に乗せるべく国連のNGOスタッフがI国へ乗り込んだのは、米軍が最後の部隊を撤収させた直後の事だった。
合衆国が国連の反対を押し切って始めた戦争は、米軍の圧倒的な戦力の前に僅か3週間で終戦を迎えた。しかし、それはあくまでI国の正規軍と米軍との間の戦闘が終結しただけに過ぎなかった。正規軍の崩壊は、逆にそれまで抑圧されていた武装勢力の一斉蜂起を促したのである。
米軍を狙った攻撃や武装勢力同士の戦闘が頻発する事態を、しかし、合衆国は決して内戦とは認めようとせず、全ては外国から侵入してきたテロ集団による擾乱(じょうらん)作戦であるという態度を崩さなかった。そして、正規軍の再編を進める事で事態を沈静化出来るとして、現地人への軍事訓練に着手した。
しかし、米軍ですら抑え切れない武装勢力の攻勢を、俄造りの軍隊が制圧出来るはずもなかった。逆に合衆国に魂を売った裏切り者に対する自爆攻撃が激化、新しい正規軍兵士の死傷者数が激増する。それでも合衆国政府は、I国正規軍が自律して治安維持活動を担える水準に達したとして、米軍の完全撤退を決定するのだった。
もちろん、この決定は武力衝突が沈静化に向かったためではなく、ただ、当初の想定を大幅に超えて長期化した駐留期間に伴う財政的な圧力と、米軍の死傷者増大に耐え切れなくなった結果に過ぎなかった。米軍の撤収が事態を収拾させるどころか、戦力の空白に伴うさらなる“内戦”の激化を招くのは誰の眼にも明らかだった。
ここに国連の総力を挙げた調停が始まる。最早合衆国も拒否権を翳(かざ)して妨害に出る事は出来なかった。国連の必死の説得は内戦の波及を恐れていた周辺諸国を動かし、I国の武装勢力への圧力は一気に強化された。こうして周辺諸国の国境封鎖によって武器の供給を断たれた各武装勢力は、ようやく和平交渉のテーブルに就く事を受け入れる。
国連の努力は実を結ぶかに見えた——
|
|
|
|
|