|  |
|
|
|
|
|
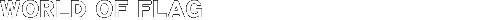
FLAG外伝 第1章 /野崎 透
2.戦いと報道(5)
カメラマンは現実と向き合うのが仕事だ。特に紛争地では、カメラマンは目を背けたくなるような醜悪な現実とも向き合わねばならない。
命懸けで悲惨な現実と向き合い、その中から真実を写し撮らねばならない。逃げる事は出来ない。
それが戦場カメラマンの仕事。しかしその中で、多くのカメラマンが心を押し潰され、狂気の中へと逃げ道を求めていくのだった——
「やり過ぎね」——その声はやり場の無い怒りに満ちていた——「あの人達、クフラの宮殿前にも検問所を作ったのよ」
しかし、角張った独り言は酒場の湿った空気に吸い込まれていくばかりで、誰もその怒りに応えようとしない。
赤城はゆっくり顔を上げて声の方を見た。背の高い痩せた女が一人、短く刈り上げた髪を覆う土埃を払おうともせずに鋭くカウンターを見つめている。もちろん赤城はその女を知っていた。リサ・ガードナー。これまでも幾度となく同じ紛争地で、スクープを競ってきた馴染みのカメラマンだ。
リサはいつもの席に陣取っていた。取材でレンズに付着した埃を吹き払っている最中だったのだろう、右手に大型のブロアーが握り締められている。しかし、唐突に蘇って来た怒りに心を引き剥がされ、作業は一時置き去りされていた。
赤城はふっと視線を逸らすと、見るとも無しに店内を見回した。窓一つ無い半地下の酒場は赤茶けた電燈に照らされ、昨夜撮影した写真のコンタクトプリントを見続けて時間の感覚を失った赤城には、今が昼なのか夜なのかほとんど区別がつかなかった。それでも古びた扉の外には、まだ午後の明りが十分残っている事だけは容易に想像がついた。そうでなければ、客がリサと赤城の二人だけのはずは無い。つまり、夜鷹揃いのジャーナリスト達が集まるにはまだ時間が早過ぎるのだ。
赤城はもう一度リサに視線を戻した。憤然とした口調とは裏腹に、その姿は何処か寂しげに見えた。自分に視線が向けられている事に気付いたのか、リサも赤城の方を見た。灰色の笑みが顔の外を覆う。
「時々、思うのよ。私達、おかしいんじゃないかって」
リサはまるで初めて赤城が居る事に気付いたかの様に静かに語り掛けた。そしてそのまま瞳を手許のカメラの上に置いた。乱雑に切り揃えられた髪が僅かにこめかみに掛かる。
リサは過剰なまでの自意識と薄いガラスの様なナイーブさとを、ほとんど剥き出しのままに持っている人間だった。それだけにその行動には、時に極端な傲慢と弱気、自分の行動に対する絶対の自信と絶望的な疑問が、ほとんど折り合いも付かないままに同居する事がある。もちろんそれらは、ほとんどのフリー・カメラマンが多かれ少なかれ持っている特性でもあった。しかし、その中でもリサは特に感情の振幅が激しかった。それだけに、自分を否定する言葉も決して珍しくはなかった。
ただ、今のリサにはそれだけではない何かが感じられた。
赤城は、コンタクトプリントの束を脇へ寄せると重い口をゆっくり押し開けた。
「どうしたんだ」
「どうしたって……」
「さっきから、独りで文句を言ってただろ」
「そうでもないでしょ」
「そうか?」
赤城は言葉を置いた。リサが僅かに視線を彷徨わせる。何か考えているのか、それとも思い出しているのか。どちらにしてもその表情には力強さはなかった。
「クフラの宮殿に行ってきたのか」
赤城はもう一度訊ねた。リサは無言のまま、再び自分のカメラに視線を置いた。
「おばあさんが、一人、門の前で五体投地(ごたいとうち)を繰り返していた」——言葉は無理矢理絞り出された様に掠(かす)れていた——「そこへ装甲車がやって来て……でも、私、喉が渇いていて、声が出なくて……」——不意にリサの瞳が小刻みに彷徨い始める——「私、声を掛けようとした……でも、その時には、もうおばあさんはぐったりと地面に倒れて……まるで、ゴムの人形みたいに……」
リサはおもむろに顔を上げて赤城を見た。
「あの人達、車を停めようともしなかった。おばあさんを轢いた事は分かったはずなのに、それなのに、あの人達……」
リサの口はどんどん早くなっていった。
「私、声を掛けようとした……でも……咽が渇いていて、それで……」
突然、リサは口を噤んだ。その視線はカメラを串刺しにしていた。
それを見た瞬間、赤城は理解した。そうだ、きっとリサは事故の現場を写しているのだと。きっとあのカメラのメモリーには老婆が轢き殺される一瞬が捉えられているのだろう。それも一枚ではない。何枚も……。
リサが本当に許せなかったのは、老婆を轢き殺した兵士達ではなかったのだ。その瞬間を撮影した自分だったのだ。
棄てるつもりか? 赤城はリサの表情を窺った。その瞳は必死にカメラを見つめていた。カメラマンとしての自分……カメラマンとしての真実……カメラマンとしての人間性……。
確かにそこに写っているのはスクープかもしれない。もし配信されれば、世界中に解放軍の非人間性を強く訴えられるだろう。
だが、写した自分はどこに居る? あの殺された老婆の側なのか? それとも、轢き殺した兵士の側なのか?
リサは悩んでいた。もちろん、同じ様な事で悩むのはこれが初めてではないのだろう。それでもやはり悩まねばならない。苦しまねばならない。これを写した自分は狂気なのか、人間性を失った機械になってしまったのかと。
赤城はリサを見つめた。もう声は掛けなかった。だいたい、言葉が見つからなかった。
ただ、一つだけ確信していた。大丈夫、リサは立ち直る——
|
|
|
|
|